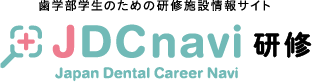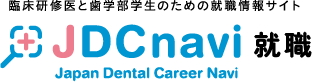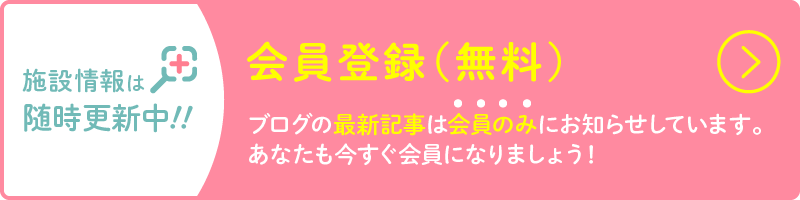歯科医師になるためには、歯科医師臨床研修に臨む方がほとんどだと思いますが、
研修では何をするのかといった具体的なイメージがもてなくて、不安になることもあるのではないでしょうか。
今回のブログでは、そんな不安を少しでも払拭していただけるように、2つの内容をお伝えしようと思います。
1、研修1年目に重点的におこなう内容と求められるスキルと知識
2、研修医の治療現場レポート
記事後半部分では、研修医の治療を実際に受けた患者さんへのインタビューもおこな
っておりますので、そのリアルな声も今後の参考にしていただけると思います。
ではさっそく、歯科学生にとって「そこが知りたい!」をみていきましょう。
臨床研修 1年目 の内容について
国家試験合格後の1年目に行われる歯科医師臨床研修1年間は、臨床スキルを磨き、実践的な経験を積む重要な時期です。
以下で、臨床研修で重点的に行うべき内容について紹介します。
1. 基本的な診療技術の習得
- 一般的な歯科診療(う蝕治療、歯周病治療、抜歯など)の技術を学ぶ。
- 歯科用器具の使い方や消毒・滅菌の手順を理解する。
2. 患者管理とコミュニケーション
- 患者とのコミュニケーションスキルを向上させる。
- 患者の病歴聴取や治療計画の説明を行う。
3. 診断能力の向上
- X線写真の読影解釈や診断技術を学ぶ。
- 口腔内の検査や評価を行い、適切な診断を下す。
4. チーム医療の理解
- 歯科医療に携わる歯科衛生士や歯科技工士との連携を学ぶ。
- 歯科以外の医療・介護チームでの治療計画や患者ケアの重要性を理解する。
5. 専門分野の基礎知識
- 歯内療法、口腔外科、矯正歯科など、各専門分野の基礎を学ぶ。
- 各分野の基本的な治療法や手技を理解する。
6. 倫理と法令の理解
- 医療倫理や患者の権利について学ぶ。
- 歯科医療に関連する法律や健康保険制度のルールを理解する。
7. 継続的な学習と自己評価
- 定期的に自己評価を行い、改善点を見つける。
- 学会やセミナーに参加し、最新の知識を得る。
大まかにこのようなことを学んでいきます。
研修医の治療技術
歯科医師臨床研修医が卒後1年目を通して、基本的な技術の習得を目指す段階にあります。
具体的には以下のようなレベルです。
1. 基本的な診療技術
- う蝕の治療(充填、根管治療など)の基礎的な手技を学び、実施することができる。
- 抜歯や歯周病治療の基本的な手技を行うことができる。
2. 審査・診断能力
- 口腔内の検査を行い、基本的な診断を下す能力が求められる。
- X線写真の読影を行い、必要な治療を計画を立案することができる。
3. 患者管理
- 患者とのコミュニケーションを通じて、病歴聴取や治療説明を行うことができる。
- 患者の不安を軽減し、信頼関係を築くスキルを身につける。
4. チーム医療
- 歯科衛生士や歯科技工士との連携を学び、チームの一員としての役割を理解する。
5. 専門分野の基礎知識
- 歯内療法や口腔外科など、各専門分野の基本的な知識を持ち、簡単な症例に対しては
治療を行うことができる。
ただし、1年目の研修医はまだ経験が浅いため、基本的な審査や治療でも指導医の監督のもとで行うことが一般的です。
いきなり複雑な症例や高度な技術を要する治療を担当することはありません。
研修を通じて、徐々に技術を向上させていくことが期待されます。
研修治療の現場(治療を受けた患者さんの声)
基本的な手技は模型実習で合格し、次は臨床実地でのCR充填を初めて行うことになった研修開始6か月目の研修歯科医師がいました。
ケースセレクション(協力患者の選定)では、数日前に右下7番の金パラインレーが脱離してしまっていた40代女性が協力してくれることとなりました。(以降Aさんと呼ばせていただきます。)
指導医監督の下で治療する際に、取材させていただきました。
当日の流れと、Aさんの感想を交えながらお伝えします。
Aさんがまず最初に感じたことは、「先生、緊張してるなぁ」とのことでした。
指導医の言葉を必死に理解しようとしているので、患者の様子をまず観察することに不手際さがあったようです。
さて浸麻が始まります。Aさんにとってこれが「きつかった」と。
この研修医の先生は、以前の浸麻では一発で浸麻を成功させていたので、
今回も大丈夫だろうと指導医もさほど心配はしていなかったそうです。
それなのになぜ「きつかった」のでしょうか。
麻酔注射後にすごく苦い味がしたそうです。すぐに歯科助手がバキュームで吸い取ってくれていますが、これって・・・。
もれてる?
苦いという事は、「薬剤が漏れている=失敗」という事では?と解ります。
案の定、指導医の歯科医師に「どこに効かせたいの?」と突っ込まれていました。
仕切り直して、指導医の熱い視線を浴びながら二本目を注射。
さて今度は大丈夫でしょう。
「あれ?苦いんですけどぉー!これって正常なの?ちょっとこわくなってきた」
とAさんは治療の後こっそりと教えてくださいました。
指導医の先生もだんだん言葉が熱くなっていました。
研修医の先生は頭が真っ白になっているのか、
指導医の質問に対してしどろもどろな返答をしていました。
(こちらの歯科医院は指導医が全部教えるのではなく、まず研修医に考えさせる指導法をとっています。そしていかなる状況でも冷静に判断ができる歯科医師に育てるのです。)
麻酔が効いているか効いていないか、わからないまま治療を続けることに。
脱離した金パラインレーの変色した合着セメントを削除し始めました。
Aさんの左手が挙手されました。何か不都合が生じたのでしょう。
「痛い!!」と感じ、思わず左手を挙げ、「痛いです」と研修医に訴えていました。
「麻酔をもう一本追加しますね」と研修医が言いますが、
「さっきと同じやり方じゃ、何本打っても効かないよ」と指導医の一言。
先ほどの浸麻の手技で、指導医は効果に疑問を感じていたようですね。
今度の浸麻は指導医がつきっきりで監督していました。
どこに射入するのか、するとどこに麻酔液が入るのか、それらを体がしっかりと覚えるように何度でも確認する研修医。
いざ、3本目。
研修医は口腔内に液漏れがない事を確認し、Aさんに味がするか確認していました。
「苦くない!!」
その事を先生に伝えると、研修医は安堵した表情で治療を再開です。
いやはや、取材している私もものすごくホッとしました。
この後は挙手されることなく治療が続けられました。
CRペーストを充填する際も、指導医から「ただ詰めるんじゃなくてどうなっているのか考えながら詰めるんだよ」と。
(皆さんはどういう事かわかりますか?隙間なく充填させるってことですか?指導医に聞いておけばよかったと思います。)
さあ、いよいよ仕上げの研磨です。
この段階では研磨ポイントの当て方、当て方による研磨力を、丁寧に指導医が教えていました。
紆余曲折ありましたが、綺麗にCR充填が終わりました。
ユニットに座ってから終了までなんと2時間かかっていました。
ベテラン歯科医師だと15分から30分以内で終わるものでしょう。
Aさんは口を開けている時間が長かったせいか、顎をマッサージしていました。
さぞお疲れだと思いますが、研修治療に協力してくれるだけのことはあって、
ニコニコと「これからも頑張ってください」と激励して下さっていました。
研修医の先生も、不慣れな治療を、指導を受けながら、また浸麻の失敗と様々な困難を乗り切ったので相当お疲れだと思います。
こうして一人前に成長していくのですね。
Aさん、指導医の先生、研修医の先生、皆さんお疲れさまでした!!
さて以上が研修医による初めてのCR充填です。
不慣れにより、時間がかかるという感じはありましたが、研修医だから下手ということはありませんでした。
実際に患者さんを患者さんとして治療するまでには、研修先でのいくつものハードルを乗り越えなければなりませんので、Aさんの体験はかなりレアなものです。
ここまでお読みいただき、研修期間になすべき事と、研修医の治療について少し理解が深まったでしょうか?
臨床研修でどのようなことがあるのか、ちょっと覗き見できたことで不安が解消されることを祈っています。
麻酔についてもっと知りたいというかたは、こちらの記事もご覧になってみてください。
【歯科医師監修】ビギナー必読!浸潤麻酔の効果が不十分で、冷や汗をかきながら治療!?
→https://www.jdc-navi.com/blog/details.jsp?id=221
【歯科医師監修】患者の信頼を得る第一歩は、浸潤麻酔の成功!
→https://www.jdc-navi.com/blog/details.jsp?id=563
取材協力:ベル歯科医院(神奈川県海老名市の管理型施設)