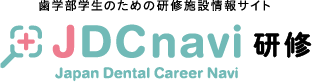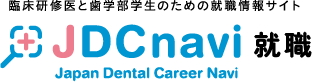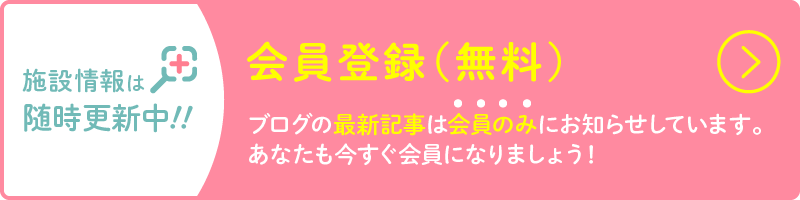歯学部生にとって、夏休みは単なる“休暇”ではありません。
CBTやOSCEを12月から1月にひかえた4年生、臨床実習の真っ最中の5年生、そして国家試験が目前に迫る6年生……それぞれの立場で、限られた夏休みをどう過ごすかは非常に重要です。
「国試の勉強もしたいけど、バイトもしないと」「遊びたい気持ちもあるけど、勉強が気になる」
そんな葛藤を抱える歯学部学生も多いのではないでしょうか。この記事では、歯学部学生の夏休みに焦点をあてて、「バイト」「勉強」「時間の使い方」をどう両立するか、学年別に分けて解説します。メリハリのある夏を過ごせば、9月以降の学習効率にも大きく影響します!
この記事を最後まで読んで、ご自身の夏休みの計画の参考にしましょう。
1. 歯学部の夏休みは意外と短い?
大学によって異なりますが、歯学部の夏休みは約4〜6週間程度。一般的な学部より短めで、5・6年生になると臨床実習が夏季期間中に一部組み込まれている場合もあります。
夏休み=自由時間 というよりは
「計画的に動かないと、あっという間に終わる」 という感覚に近いかもしれません。
つまり、長く自由な時間があるように見えて、実は「計画的に使わなければすぐ終わる」のが歯学部の夏休みです。
その限られた時間を「何に」「どれくらい」使うかが、秋以降の国試対策や精神的な余裕にもつながります。
2. 歯科学生に人気のバイトとは?
歯学部生は勉強が忙しい一方、学費や生活費のためにバイトをしている人も多数います。
夏休みはバイト時間を確保しやすい絶好のタイミング。
以下は、歯科学生に人気のバイトの例です:
◎ 歯科医院での助手・受付バイト
・器具や処置を間近で見られるため、国家試験対策にも直結
・現場での感染対策や患者対応を実地で学べる
◎ 家庭教師・塾講師(理系科目)
・高時給で、教えることが自分の勉強の復習にもなる
・夏期講習中心の短期集中型も選びやすい
◎ 模試監督・イベントスタッフなど短期バイト
・学業に支障なく働けて、スケジュール調整がしやすい
・人間関係のストレスが少なめ
中でも歯科医院バイトは非常に実践的で、国家試験で問われる処置や器具名などを“実物”で覚えることができます。夏休み限定の短期採用もあるので、気になる医院には早めに問い合わせましょう。
3. 夏こそ国試勉強の先取りチャンス!
夏休みはまとまった時間が取れる数少ないチャンス。国試対策においては、「早く始めた人が有利」という事実は変わりません。学年ごとに夏休みの勉強の進め方を見ていきましょう。
【4年生】CBT・OSCEの勉強が国試モードへの転換期
・CBTで出題される範囲を確認し、「なぜそうなるか」を理解する
・病態や治療の流れを“ストーリーで覚える”クセをつける
・OSCE対策で学んだ内容をアウトプット(声に出して説明)する習慣をつける
・国試に頻出の項目(感染対策、公衆衛生、薬理など)から少しずつ先取りしてみる
CBTと国家試験は出題形式こそ違いますが、内容的には重なる部分が多いため、「CBTを国試対策の一部と捉える」ことで先取り対策ができ、勉強効率が上がります。ですから、この夏は12月から1月に行われるCBT・OSCEの試験対策をしっかりやりましょう!
【5年生】本格的に国試勉強を開始する時期
・基礎科目(解剖・生理・病理など)を国家試験レベルで整理し直す
・過去問を使って出題傾向をチェックし始める(最初は理解重視)
・「自分専用のまとめノート」や暗記カードを作成して繰り返し復習
・苦手科目・単元を夏の間に1つでも克服する!
5年生はまだ国試まで時間があるとはいえ、ここで差がつき始めます。
普段の生活よりは時間に余裕のある夏休みだからこそ、最低でも1日2時間の“国試タイム”を確保して、習慣化しておきましょう。また以前受けたCBTで自分の得意不得意を再確認し、復習するのも一つの手です。
【6年生】実戦力と得点力を鍛える
・過去問を10年分解く(まずは正確に理解することが目的)
・模試を受けて、実力チェックと弱点把握
・苦手分野を集中的に対策し、知識の穴を埋める
・アプリ・暗記カード・語呂などを駆使して“忘れない仕組み”を作る
6年生にとって夏はまさに“国試勝負の前半戦”。この時期にしっかり仕上げておけば、直前期は焦らず安定して過ごせます。
4. バイトと勉強、両立するための時間管理術
夏休み中は、自由な時間がある反面、自己管理が難しくなる時期でもあります。バイトも勉強も中途半端にならないよう、以下のような工夫がおすすめです。
ポイント1:先に“勉強時間”を確保する
バイトのシフトを組む前に、「毎日●時〜●時は国試対策」と決めておくことで、学習時間が確保できます。夜型・朝型など、自分のリズムに合わせて調整を。
ポイント2:スキマ時間を「暗記タイム」に活用
通勤電車、バイトの休憩時間、就寝前など、スマホで暗記カードアプリや動画講義を見れば、まとまった時間がなくても勉強できます。
ポイント3:長期と短期の両方でスケジュールを立てる
まず、長期計画でざっくりと目標スケジュールを立てます。そしてそれを細分化します。
例えば、週の初めに「今週の目標」のように短期目標を決め、週末に達成度を振り返る習慣をつけます。
すると長期計画にずれが生じにくく、ペースを保ちやすくなります。
5. モチベーション維持のためのアイデア
夏は誘惑も多く、だらけやすい時期。モチベーションを保つには、ちょっとした工夫が大切です。
・SNSで国試アカウントをフォローして刺激を受ける
・勉強記録をインスタや手帳に可視化する
・友達と「毎日〇問解くチャレンジ」などミニ目標を立てる
・バイト先やカフェで気分転換しながら勉強する
・合格後の自分へのご褒美を考えておく
「今日は30分だけでもOK」という気持ちで、勉強と余暇のバランスを取りながら、継続することが最大のカギです。
まとめ:夏休みをどう使うかで差がつく!
歯学部学生の夏休みは、国試対策を本格化させる“勝負の時期”でもあります。
バイトで収入や社会経験を得つつ、国家試験の準備も着実に進めることで、秋以降の学習に余裕が生まれます。
・4年生はCBTとOSCE対策から国試を意識
・5年生はインプットとアウトプットのサイクルを確立
・6年生は模試・過去問を中心に“得点力”を仕上げる
限られた夏休みを有効活用することで、「早く始めてよかった」と感じられる冬が待っています。
この夏をどう使うかによって、来年2月の結果は左右します。
バイトも、遊びも、勉強も。全部あきらめずに、計画的にやればきっとできる!
あなたの夏が、合格への第一歩になりますように。
編集後記
当ブログを、1年目の研修医3名に事前に読んでもらい、感想を聞いてみました。
Aさん:私はこれに近い状態で学生生活を送っていました!自分との闘いなので、自分を常に何かで満たすようにしていました。今思い返しても、大事なことだったと思います。
Bさん:いやいや、ものすごく理想だけど、私はここまではできませんでした。でも、絶対に頑張らないといけない時が来るので、その時に踏ん張れる人や自分の勉強法が確立できていることも大事だと思います。
Cさん:学生時代に知りたかったです(笑)。自分でこのことに気が付いたのは6年生だったので、ラストスパートと同時に時間管理を身につけるのが大変でした。
このように、様々な反応がありました。紹介したブログの内容が基準とは言いませんが、現在どのような学生生活を送ればいいのかわからなくなっている人や、自分の学生生活を見直したい、後押ししてほしい!といった方の参考になれば幸いです。
こちらのブログもぜひご覧ください
【国試合格者はタイムスケジュールを活用】こうして合格者は長期休みを乗り切った
→https://www.jdc-navi.com/blog/details.jsp?id=883
国試合格にむけて参考にしたい「国試合格者のリアルな1日」を大公開
→https://www.jdc-navi.com/blog/details.jsp?id=903
【対策必須!】 「CBT」と「OSCE」って?「歯科医師国家試験」に影響があるの?
→https://www.jdc-navi.com/blog/details.jsp?id=1023