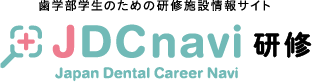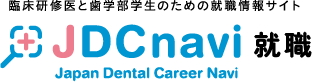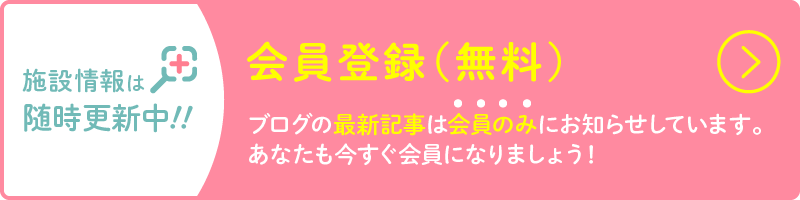臨床実習や研修が始まると、必ずぶつかる壁があります。
「患者さんを目の前にして、何から考えればいいか分からない」
「検査データは揃ったけど、どう治療方針に落とし込めばよいのか?」
「指導医に『じゃあ治療計画を立ててみて』と言われて固まった」
教科書には各疾患の治療法は書いてあるけれど、「実際の患者さんにどう適用するか」は書いていません。
この記事では、歯学部生・研修医の皆さんが臨床現場で即実践できる治療計画立案の思考プロセスを、具体例とともに徹底解説します。
本記事は、複数の大学病院・臨床研修施設での指導経験を持つ歯科医師の監修のもと、研修医が実際に「分からなかった」「困った」ポイントを重点的に解説しています。
治療計画とは何か?臨床における位置づけ
治療計画の定義(臨床的定義)
治療計画とは、
「診断に基づき、患者の問題を解決するための具体的な治療手段・順序・期間を体系的に整理したもの」です。
なぜ治療計画が重要なのか?
1. 治療のゴールを明確にする
・「とりあえず削って詰める」では不十分
・「なぜこの治療が必要か」を論理的に説明できる
2. 優先順位をつける
・すべてを一度に治療できない場合の判断基準
・応急処置 vs 根本治療の区別
3. 患者・指導医とのコミュニケーションツール
・口頭だけでなく、書面で共有することで認識のズレを防ぐ
・インフォームドコンセントの基盤
4. 保険請求・医療訴訟対策
・診療録として記録に残す
・「なぜこの治療を選択したか」の根拠を示す
教科書と臨床のギャップ
臨床では「教科書通り」にいかないことの方が多いのです。
【8つのステップ】治療計画立案の実践プロセス
STEP 1: 情報収集(問診・視診・検査)
↓
STEP 2: 問題リストの作成(POSの活用)
↓
STEP 3: 診断(疾患名・病態の確定)
↓
STEP 4: 原因分析(なぜそうなったか)
↓
STEP 5: 治療ゴールの設定(短期・長期=治療後のケアも含む)
↓
STEP 6: 治療選択肢の列挙(複数案)
↓
STEP 7: 選択肢の評価・比較
↓
STEP 8: 最終治療計画の決定・提示
STEP 1: 情報収集
目的
患者の全体像を把握し、治療計画の材料を集める
収集すべき情報
A. 主訴・現病歴
・「いつから」「どこが」「どのように」「何をして」
・OPQRST法の活用
‥Onset: いつから
‥Provocation: 何で悪化/改善するか
‥Quality: どんな感じ(痛み・しみる・違和感)
‥Region: 場所
‥Severity: 程度(VAS)
‥Time: 時間経過
B. 既往歴・現症
・全身疾患: 糖尿病、高血圧、骨粗鬆症、肝疾患など
・服薬: 抗凝固薬、ビスホスホネート製剤、ステロイド
・アレルギー: 薬剤、ラテックス、金属、食品
・喫煙・飲酒: 歯周病・インプラントのリスク因子
C. 歯科治療歴
・過去の治療内容
・苦手な処置(麻酔、削る音など)
・治療の中断歴(→コンプライアンスの予測)
D. 生活習慣・社会的背景
・職業(→通院可能な曜日・時間)
・食生活(→う蝕・酸蝕のリスク)
・ブラッシング習慣
・経済状況(→保険 or 自費の選択に影響)
E. 患者の希望・価値観
・「痛みを取りたい」(機能重視)
・「見た目を綺麗にしたい」(審美重視)
・「なるべく早く終わらせたい」(期間重視)
・「歯を抜きたくない」(保存重視)
研修医がやりがちな失敗
・主訴だけ聞いて、全身状態を聞き忘れる
・ 問診票に書いてあることを鵜呑みにして、追加質問しない
・「患者の希望」を聞かずに、医療者側の判断だけで進める
STEP 2: 問題リストの作成
従来の「疾患別」ではなく、患者の「問題」を中心に整理する方法。
問題リストの作り方
1. すべての問題を書き出す
・大きな問題も小さな問題も、すべて列挙
・この段階では優先順位をつけない
例: 50代男性の問題リスト
#1 右下6番 C4(主訴: 痛み)
#2 右下7番 Per(根尖病巣)
#3 左上4番 C2
#4 全顎的な歯周炎(BOP 60%, PPD 4-6mm)
#5 前歯部の審美不良(CR変色)
#6 咬合不正(左側臼歯部欠損による片側咬合)
#7 不良補綴物(右上567 Br 適合不良)
#8 プラークコントロール不良(PCR 80%)
#9 喫煙習慣(20本/日 × 30年)
#10 糖尿病(HbA1c 7.8%、コントロール不良)
#11 不規則な通院歴(過去に治療中断)
2. 問題の関連性を考える
・どの問題が原因で、どの問題が結果か
・連鎖的に悪化している問題はないか
【因果関係の例】
#9 喫煙 ──→ #4 歯周炎 ──→ #6 咬合不正
#10 糖尿病 ──→ 治癒遅延のリスク
#8 PCR不良 ──→ #1, #3 齲蝕の再発リスク
3. 優先順位をつける
・P(Problem): 緊急性・重要性
・A(Active): 現在進行中
・I(Inactive): 経過観察中
STEP 3: 診断
目的
問題リストの各項目に、正確な診断名をつける
診断の書き方
よい例
#1 右下6番 残根状態、慢性根尖性歯周炎
(パノラマX線にて根尖部透過像あり、打診痛(+))よくない例
#1 右下6番 虫歯
(診断根拠が不明、病態が曖昧)
研修医へのアドバイス
・診断名は具体的に(「虫歯」ではなく「C3」「C4」)
・必ず診断根拠を併記(検査所見、画像所見)
・不明な場合は「疑い」「要精査」と正直に書く
STEP 4: 原因分析
目的:「なぜこうなったのか」を考える → 再発防止につながる
原因分析のフレームワーク
Keyes の三要素(う蝕の例)
宿主(歯質)
↓
細菌 ×────── 糖質
この患者さんはどこに問題があるか?
う蝕多発患者の原因分析
【直接原因】
・プラークコントロール不良(PCR 80%)
・糖質摂取頻度が高い(間食、甘い飲料)
【間接原因】
・ブラッシング指導を受けたことがない
・仕事が忙しく、食生活が不規則
・歯科受診の優先順位が低い(痛くなるまで放置)
【背景要因】
・歯科に対する知識不足
・経済的に定期検診を受ける余裕がなかった
重要な視点
原因を解決しない限り、治療しても再発する。
→ 治療計画には「原因除去」も含める
STEP 5: 治療ゴールの設定
目的「どこまで治すか」の基準を明確にする
短期ゴール vs 長期ゴール
例: 前述の50代男性のゴール設定
短期ゴール(3ヶ月)
1.右下6番の疼痛除去(抜髄 or 抜歯)
2.急性歯周炎の改善(SRP)
3.PCRを30%以下に改善
4.糖尿病の主治医と連携(HbA1c 7.0%以下を目標)
長期ゴール(1年)
1.全顎的な歯周治療完了(PPD 3mm以下)
2.欠損部の補綴(咬合の回復)
3.審美治療(希望があれば)
4.3ヶ月ごとのメインテナンス
STEP 6: 治療選択肢の列挙
目的:複数の治療オプションを考える(1つに絞らない)
なぜ複数の選択肢が必要か?
1.医学的に複数の正解がある(エビデンスレベルが同等)
2.患者の価値観によって最善策が変わる
3.インフォームドコンセントの前提
例: 深いう蝕(C3/C4)の選択肢
STEP 7: 選択肢の評価・比較
目的:各選択肢を客観的に評価し、患者に提示できる形にする評価の視点(5つの軸)
1. 医学的妥当性
・エビデンスレベルは?
・成功率・予後は?
・合併症のリスクは?
2. 患者の全身状態との適合性
・糖尿病患者にインプラントは?
・抗凝固薬服用中の抜歯は?
・高齢者への侵襲的治療は?
3. 期間・通院回数
・患者の通院可能頻度は?
・仕事・育児との両立は?
4. 費用
・保険 vs 自費
・患者の経済状況は?
5. 患者の希望・価値観
・「歯を残したい」
・「見た目を綺麗に」
・「早く終わらせたい」
評価表の作成例
【#1 右下6番 C4 の治療選択肢評価】
選択肢①: 根管治療 + Cr
- 医学的妥当性: ○(保存可能な歯質あり)
- 全身状態: ○(制約なし)
- 期間: △(4〜5回、2ヶ月)
- 費用: ○(保険適用)
- 患者希望: ◎(歯を残したい)
選択肢②: 抜歯 + インプラント
- 医学的妥当性: ○
- 全身状態: △(糖尿病コントロール要)
- 期間: ×(6ヶ月以上)
- 費用: ×(40万円)
- 患者希望: △(高額がネック)
→ 選択肢①を第一選択として提案
STEP 8: 最終治療計画の決定・提示
目的:評価結果をもとに、患者に分かりやすく説明し、同意を得る
治療計画書の必須項目
1.問題リスト(何を治すのか)
2.治療目標(どこまで治すのか)
3.治療方法の選択肢(複数提示)
4.推奨する治療方法(理由も明記)
5.治療の順序・期間(フェーズ分け)
6.費用の概算
7.リスク・合併症
8.治療しなかった場合の予後
説明のコツ(研修医向け)
よい例
・「今の状態はこうで、このまま放置すると〇〇のリスクがあります」
・「治療方法はA・B・Cがあり、それぞれメリット・デメリットは...」
・「私の推奨はAですが、最終的には〇〇さんに決めていただきます」
よくない例
・「虫歯があるので削ります」(理由・選択肢の説明なし)
・「教授がこう言ってたので」(主体性がない)
・専門用語を多用して患者が理解できない
研修医が陥りやすい落とし穴
1. 「教科書の治療」に固執する
→ 患者の個別性を無視してはいけない
2. 主訴だけに囚われる
→ 潜在的な問題も見逃さない
3. すべてを一度に治そうとする
→ フェーズ分けして優先順位を
4. 患者の希望を聞かない
→ 押し付けの治療は失敗する
5. 指導医に相談せず独断で決める
→ 必ず上級医にプレゼンして確認
チェックリスト: 治療計画の質を自己評価
研修医の皆さん、自分の立てた治療計画を以下でチェックしてみてください。
・問題リストは漏れなく作成できているか?
・各問題に診断名と根拠が明記されているか?
・原因分析ができているか?
・短期・長期のゴールが明確か?
・治療選択肢を複数考えたか?
・各選択肢のメリット・デメリットを説明できるか?
・患者の全身状態・希望を考慮したか?
・治療の順序・期間は現実的か?
・費用の概算を提示できるか?
・指導医にプレゼンして確認を得たか?
10項目中7項目以上クリアできていれば合格ラインです!
このアーティファクトを臨床実習・研修で常に参照してください。
【ケーススタディ】実際の症例で治療計画を立ててみよう
理論だけでなく、実践例で思考プロセスを体験してみましょう。
ケース1: 20代女性「前歯が欠けた」
初診時情報
・主訴:「昨日転んで前歯が欠けた。明日から就職活動なので早く治したい」
・現症:右上1番 エナメル質〜象牙質の破折(露髄なし)
打撲痛(+)、動揺(-)
他の歯に問題なし
・既往歴:特記事項なし
・希望:「できれば今日中に見た目を治してほしい」
STEP 1-2: 問題リスト
#1 右上1番 歯冠破折(外傷性)
#2 審美障害(就職活動に支障)
#3 時間的制約(明日から面接)
STEP 3-4: 診断・原因
診断:右上1番 エナメル質象牙質破折(Ellis分類 Class II)
原因:外傷(転倒時に地面に顔面を打撲)
STEP 5: ゴール設定
【短期】今日中に審美的に改善
【長期】歯髄の健康維持、破折部の強度回復
STEP 6-7: 治療選択肢と評価
STEP 8: 治療計画
【第一選択】CR充填(即日)
理由:・時間的制約(就活)を最優先
・露髄していないため、歯髄保存可能
・将来的に②③への変更も可能
治療の流れ
1.今日: CR充填で審美回復
2.1週間後: 再診(歯髄の状態確認、打撲痛の消失確認)
3.1ヶ月後: 再診(変色・破折のチェック)
4.将来的に: 審美的に不満があれば②③を検討
患者への説明ポイント
・「今日は応急的な処置で、見た目は回復しますが、強度は本来の歯より劣ります」
・「硬いものを噛むときは注意してください」
・「就活が終わった後、より精密な治療も検討できます」
ケース2: 60代男性「全体的に悪い」
初診時情報
主訴:「痛いところがいくつかある。全体的に治したい」
現症:・右下6番 C4(残根、主訴)
・左上6番 Per(根尖病巣)
・全顎的歯周炎(PPD 4-7mm、BOP 70%)
・多数歯にC2-C3
・右上567欠損(無補綴)
・左下7番欠損
既往歴:糖尿病(HbA1c 8.2%)、高血圧
喫煙: 30本/日 × 40年
希望:「痛みを取って、ちゃんと噛めるようにしたい」
問題点(研修医が考えるべきこと)
あなたならどこから治療しますか?
STEP 1-2: 問題リスト(優先順位付き)
【緊急性: 高】
#1 右下6番 C4、自発痛(主訴)
#2 全顎的歯周炎(活動性)
【重要性: 高】
#3 糖尿病コントロール不良
#4 喫煙(歯周病・創傷治癒のリスク因子)
#5 咬合不正(臼歯部欠損)
【経過観察可】
#6 多数歯のう蝕(C2-C3、無症状)
#7 左上6番 Per(無症状)
STEP 3-4: 診断・原因分析
診断:
#1 右下6番 残根状態、急性歯髄炎
#2 広汎型慢性歯周炎(Stage III, Grade C)
#3 2型糖尿病(コントロール不良)
原因:
【直接原因】
- プラークコントロール不良
- 長期間の歯科受診中断
【リスク因子】
- 糖尿病 → 歯周病の増悪因子
- 喫煙 → 歯周病の増悪・創傷治癒遅延
- 欠損放置 → 咬合負担の偏り
【背景】
- 歯科に対する意識が低い
- 「痛くなければOK」という認識
STEP 5: ゴール設定
【短期ゴール(3ヶ月)】
1. 疼痛の除去
2. 歯周炎の活動性をコントロール
3. PCR 20%以下
4. 糖尿病の主治医と連携(HbA1c 7.5%以下目標)
5. 禁煙指導開始
【長期ゴール(1年)】
1. 歯周病の安定(PPD 3mm以下、BOP 20%以下)
2. 欠損部の補綴(咬合回復)
3. う蝕治療完了
4. SPT移行(3ヶ月ごと)
STEP 6-7: 治療フェーズ分け
【Phase 1: 緊急処置】(1回目)
・右下6番の疼痛管理(抜髄 or 抜歯)
・患者教育(病状説明、TBI)
【Phase 2: 原因除去療法】(2〜3ヶ月)
・歯周基本治療(SC/SRP)
・プラークコントロールの確立
・糖尿病主治医への診療情報提供
・禁煙指導・支援
※この期間、う蝕治療は保留
【Phase 3: 再評価】(3ヶ月後)
・歯周組織の改善度をチェック
・抜歯適応歯の判定
・治療計画の見直し
【Phase 4: 修復治療】(4〜8ヶ月)
・う蝕治療(保存可能歯の充填・補綴)
・根管治療が必要な歯の処置
・保存不可能歯の抜歯
【Phase 5: 補綴治療】(9〜12ヶ月)
・欠損部の補綴設計
・咬合の回復
・仮義歯による咬合調整
・最終補綴物の装着
【Phase 6: メインテナンス】(1年以降)
・3ヶ月ごとのSPT
・プラークコントロールの維持
・糖尿病管理の継続確認
STEP 8: 治療計画の説明ポイント 患者への説明例:
「〇〇さん、まず痛みは今日取りますが、全体を治すには時間がかかります。
一番の問題は歯周病です。これは糖尿病や喫煙と深く関係しています。
いくら歯を治しても、土台の歯ぐきが悪ければまた悪くなってしまいます。
ですから、最初の2〜3ヶ月は歯ぐきの治療を優先します。
その間に歯磨きの練習もしていただきます。
歯ぐきが良くなってから、虫歯の治療や、噛めるようにする治療に進みます。
全体で1年ほどかかりますが、焦らず一緒に治していきましょう。
内科の先生とも連携しますので、糖尿病の管理も並行してお願いします。
できれば禁煙も検討していただけると、治療の成功率が上がります」
研修医が考えるべきポイント
1.なぜ、う蝕治療を後回しにするのか? → 歯周病が活動性の場合、修復物を入れても予後不良 → 原因(プラーク、リスク因子)を先にコントロール
2.糖尿病への対応は? → 内科医に診療情報提供書を作成 → 観血処置前にHbA1cを確認(7.0%以下が望ましい) → 抗菌薬の予防投与を検討
3.喫煙指導はどうする? → 無理強いせず、まずは情報提供 → 「禁煙すると治りが良くなる」と具体的メリットを説明 → 禁煙外来の紹介も選択肢に
4.患者のコンプライアンスが心配な場合は? → 治療期間を短縮する代替案も用意 → 通院が途絶えた場合のリスクを事前に説明 → 家族の協力を得る
よくある研修医の質問Q&A
Q1: 治療計画は誰が立てるべきですか?研修医が立てていいのでしょうか?
A: 研修医が立案し、指導医が監修・承認するのが基本です。
・まず自分で考えてプレゼンする
・指導医からフィードバックを受ける
・修正して患者に説明 この過程が最も勉強になります。
最初から指導医任せにしないことが重要です。
Q2: 患者さんが「先生にお任せします」と言われたらどうすれば?
A: それでも選択肢は説明すべきです。
・「お任せいただけるのはありがたいですが、治療方法にはいくつか選択肢があります。
それぞれメリット・デメリットがありますので、一度説明させてください」
患者の同意なしに治療を進めることは、法的にもリスクがあります。
Q3: 治療計画を立てたのに、指導医に全否定されました…
A: よくあることです!落ち込む必要はありません。
・なぜその計画が不適切だったのか、理由を聞く
・指導医の考え方を学ぶチャンス
・次回は同じミスをしないようメモを取る
指導医によって考え方が違うこともあります。複数の視点を学べるのは研修期間の特権です。
Q4: 教科書的な治療と、実際の治療が違うことに戸惑います
A: これが臨床の難しさであり、面白さです。
・教科書は「理想的な条件下」での話
・実際には、患者の全身状態・経済状況・希望が関わる
・「ベストではなくベター」を選ぶことも多い
この判断ができるようになることが、臨床医としての成長です。
Q5: 患者さんが治療計画を拒否したらどうすれば?
A: まず理由を聞きましょう。
・費用が心配? → 保険診療の範囲を提示
・期間が心配? → 治療を分割、優先順位を変更
・恐怖心がある? → 無痛治療の工夫、段階的なアプローチ
患者の不安や事情を理解せずに説得しても逆効果です。
Q6: 複数の問題がある患者で、何から手をつけるべきか分かりません
A: 優先順位の原則:
・生命に関わる問題(急性感染、重度全身疾患)
・疼痛・急性症状(主訴への対応)
・原因除去(歯周病、プラークコントロール)
・機能回復(咬合、欠損補綴)
・審美改善(変色歯、形態修正)
ただし、患者の希望が強い場合は順序を調整することもあります。
Q7: 保険診療と自費診療、どう説明すればいいですか?
A: 両方の選択肢を提示するのが原則です。
・まず保険診療の範囲で可能な治療を説明
・より審美性・耐久性を求める場合の自費オプションを紹介
・「自費を勧める」のではなく「選択肢として提示する」
押し売りと思われないよう、中立的な説明を心がけましょう。
Q8: 治療計画書は毎回書かないといけませんか?
A: 初診時と、治療方針が変わった時には必須です。
・簡単な処置(1本の充填など)では省略可
・複数回にわたる治療、高額な治療では必ず文書化
・カルテへの記載も忘れずに
「言った・言わない」のトラブル防止のためにも重要です。
Q9: 患者さんが途中で来なくなった場合は?
A: 中断患者への対応:・電話やハガキで確認(3ヶ月以内)
・中断のリスクをカルテに記載
・再来時には改めて現状説明
無理に来院を強要することはできませんが、リスクは伝えるべきです。
Q10: 指導医がいない場面で判断を求められたら?
A: 自信がない場合は、無理に判断しないことも大切です。
・「指導医に確認してから回答します」と正直に伝える
・応急処置だけして、本格的な治療は保留
・電話で指導医に相談
研修医が独断で進めて、後で問題になるケースもあります。
臨床実習・研修で使える治療計画テンプレート
研修医の皆さんが実際に使えるテンプレートを用意しました。
このフォーマットに沿って記入すれば、指導医へのプレゼンもスムーズです。
治療計画書テンプレート
【患者基本情報】
氏名:
年齢・性別:
初診日:
主訴:
【既往歴・服薬】
全身疾患:
服薬:
アレルギー:
喫煙・飲酒:
【問題リスト】
#1
#2
#3
#4
#5
【診断】
#1
診断根拠:
#2
診断根拠:
【原因分析】
直接原因:
リスク因子:
背景要因:
【治療目標】
短期ゴール( ヶ月):
1.
2.
3.
長期ゴール( 年):
1.
2.
3.
【治療計画】
Phase 1(応急処置):
Phase 2(原因除去療法):
Phase 3(再評価):
Phase 4(修復・補綴治療):
Phase 5(メインテナンス):
【費用概算】
保険診療:約 円
自費診療(希望時):約 円
【治療期間】
通院回数:約 回
期間:約 ヶ月
【リスク・注意事項】
・
・
【患者の同意】
□ 治療計画について説明し、同意を得た
□ 代替案についても説明した
□ 治療しなかった場合のリスクも説明した
説明日: 年 月 日
説明者:
患者署名:
このテンプレートをコピーして、電子カルテやノートに貼り付けて使ってください。
まとめ:治療計画立案で大切な3つの心構え
1. 患者中心の思考
医療者の都合ではなく、患者のゴールを最優先に。
2. 論理的な思考プロセス
感覚ではなく、根拠に基づいた判断を。
3. 柔軟性と謙虚さ
計画は変わることもある。分からないことは素直に相談を。
計画の立案は、歯科臨床の核心です。
最初はうまくいかなくて当然です。 指導医に何度も修正されながら、少しずつ身につけていくものです。
この記事を臨床実習・研修の現場で何度も読み返し、実践してください。
症例を重ねるごとに、必ず「考える力」が養われていきます。
あなたの成長を応援しています。頑張ってください!
著者情報
JDCnavi編集部
・歯学部学生・歯科医師専門の情報メディア
・現役歯科医師・研修医による監修体制
・進路相談実績あり
監修者情報
鈴木彰 医師
・神奈川県「ベル歯科医院」院長
・歯科医師歴30年以上
・ 1986年 東京医科歯科大学歯学部卒業
・ 1986年〜1989年 東京医科歯科大学歯学部 附属病院顎口腔機能治療部
・ 1989年 「ベル歯科医院」開設
・ 専門:一般歯科、予防歯科