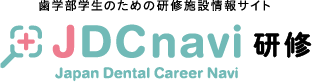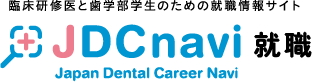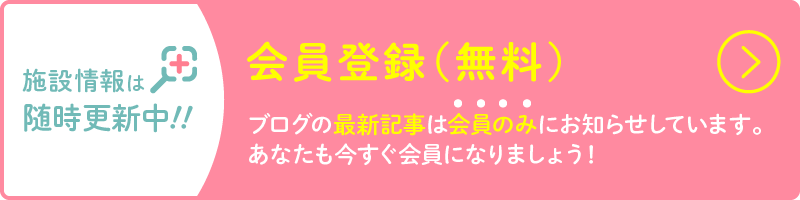理想と現実のギャップが物語るもの
「歯学部 進路」「歯科医師 就職」「大学院 歯学部」これらは歯学部5-6年生の皆さんが最も検索するキーワードです。
私たちJDCnaviでは、2025年8月に「X」を通じて歯学部学生と卒業生を対象とした進路に関する独自アンケート調査を実施しました。回答者数約30名から回答が得られ、その結果、驚くべき事実が明らかになりました。
一見すると「わずか7%」に見えるこの差異。しかし、この数字の理由にはどんな理由があるのでしょうか。歯科業界の構造的な問題と、学生が知らない現実が隠されているのです。
この記事では、現役歯科医師と歯学部教授の監修のもと、このギャップがどのようにうまれたか、背景を含めて解明していきます。最後までお見逃しなく!
なぜ「臨床医希望」の比率が卒業後に低くなるのか?5つの要因分析
要因1:臨床研修での現実体験による方向転換
歯科医師臨床研修制度の影響
歯学部6年生の8割以上が臨床医を希望するのは当然です。6年間の歯学教育の大部分が臨床を前提としているからです。
しかし、卒業後の臨床研修で初めて「本当の歯科臨床」を体験した際に、約7%の人が方向転換を決意します。
現役研修医の証言: 「学生時代の臨床実習と実際の研修医業務は全く違いました。責任の重さ、患者さんとの距離感、長時間労働などなど。理想と現実のギャップに戸惑い、大学院進学を選択しました」
要因2:歯科医師過剰時代の就職難
2025年現在の歯科医師就職事情
・歯科医師数:約10万7千人(2024年厚労省データ)
・新規参入:年約2,000人
・廃業・引退:年約1,500人
この数字が示すのは、実質的な歯科医師増加です。優良な歯科医院への就職競争は年々激化しており、希望する条件での就職が困難なケースが増えています。
実際にマッチングプログラムでアンマッチになり、当事務局へのお問い合わせが、10月ころから例年多数寄せられます。
要因3:大学院進学の「逃げ道」化
大学院希望10%→実際18%の8%増加の背景
この8%増加は決して「研究への情熱」だけではありません。
大学院選択の真の理由(複数回答):
・臨床への不安・適性への疑問:45%
・就職先が見つからない:30%
・専門医取得による差別化:60%
・研究への純粋な興味:25%
監修医師のコメント: 「近年、大学院は『臨床からの避難場所』としての機能も持つ所もあるようです。これ自体は悪いことではありませんが、明確な目的意識なしに進学すると、卒業後により深刻な進路の悩みを抱えることになります。大学の体制によっても、大学院に残る残らないというのは意味合いが変わってくるので要注意です。国立大学・私立大学という違いだけでも、院生を確保する大学院側の意味合いが違うので、学生の皆さんはしっかりと下調べをしましょう。特記する院へ進む学生の考え方は、国立大学では院へ進むことが『普通』と考えるのに対して、私立大学では院へ進むのは『目的がある』という文化的な体制の違いがあるのです。」
要因4:専門医制度の影響
専門医取得のための大学院進学増加
2018年から始まった新専門医制度により、専門医資格取得のハードルが上がりました。多くの専門分野で大学院での研究経験や論文発表が実質的に必要となり、大学院進学を選択する卒業生が増加しています。
要因5:経済的要因と開業準備期間
開業資金準備のための大学院選択
歯科医院開業には平均5,000-1億円の資金が必要と言われています。卒業直後すぐの開業は現実的でなく、大学院での期間を「開業準備期間」として活用するケースもあるようです。
「7%」が示す歯科業界の構造的問題
問題1:歯学教育と臨床現場のミスマッチ
教育現場での理想 vs 臨床現場の現実
歯学部教育は主に大学病院での症例を基準としています。が、実際の歯科医院では
・ 予防歯科・メンテナンスが中心
・ 患者対応・地域特性・クレーム処理
・ 経営的視点の必要性
・ デジタル技術への対応
これらの現実を学生時代に十分学ぶ機会は限られています。
問題2:キャリアパスの多様性不足
「臨床医 or 研究者」の二択構造
現在の歯学教育では、卒業後の選択肢が上記のように限定的に提示されがちです。
実際には
・ 歯科医療機器メーカー
・ 歯科材料開発
・ 歯科医療IT企業
・ 行政(保健所・厚労省等)
・ 歯科医療コンサルティング
など、多様なキャリアパスが存在しますが、情報不足により選択されにくいのが現状です。
監修医師のコメント:歯科衛生品を開発する企業にも、実は歯学部出身の人がいるのです。ある歯科医師は臨床研修後臨床医として勤務しながら『治療ではない歯科の向き合い方があるのでは?』『どうしたら虫歯を効率よく防げるかな?』と、製品開発をする企業へのアドバイザーとして活躍されている人もいるのです。
問題3:メンタルヘルス支援の不足
進路変更への罪悪感とサポート体制
「6年間学んだのに臨床医にならないのはもったいない」という価値観が根強く、進路変更に対する心理的ハードルが高いことも要因の一つです。
現役研修医の証言:「私の友人は、『歯学部に入ったのだから、歯科医にならなくてはいけないんだ』と、かなり思い詰めていました。6年という長い期間、高い学費・・・、確かに後戻りはできない環境です。でも、興味がなくて歯学部に入ったわけではないので、上記のように、臨床医ではなくても歯学部で学んだことが活かせる職業があることを当時知っていたら、アドバイスをすることができたと思います。」
現役歯科医師が語る「進路選択で後悔しないための3つのポイント」
ポイント1:「消去法」ではなく「積極的選択」を
NG例:「臨床が嫌だから大学院」
OK例:「○○分野を極めたいから大学院」
進路選択は「逃げ」ではなく「攻め」の姿勢で行うことが重要です。
ポイント2:実際に働いている人の話を聞く
情報収集の重要性
・ 臨床医を目指す→歯科医院でアルバイト経験、先輩研修医との交流、施設見学
・大学院を目指す→現役院生・修了生との面談
・企業を目指す →OB・OG訪問の積極活用、企業側への質問
ポイント3:「Plan」をいくつか持っておく
柔軟性のある進路設計
最初の選択が全てではありません。臨床経験後の大学院進学、研究経験後の臨床復帰など、キャリアチェンジは可能です。
監修医師のコメント:「キャリアチェンジといえば、当院で1年の研修を終えた女性歯科医師が、「歯科麻酔科医になりたい」と研修半ばの段階で相談してきました。
とても真剣に考え、また常に先のことを考えながら行動する研修医でしたので、ぜひ残ってほしい気持ちもありましたが、熱意がとても感じられたので、どうしたら『歯科麻酔科医』になれるのかアドバイスもしましたし、友人の歯科麻酔科医と話をする機会も作りました。きっと今頃、大学病院で歯科麻酔科医としての専門分野でしっかり学んでいることでしょう」
歯学部学生が今すぐできる「進路ミスマッチ防止」対策
対策1:5-6年生の臨床実習を最大限に体験
チェックポイント:
・患者さんとのコミュニケーションは楽しいか?
・長時間の診療に集中できるか?
・治療結果に達成感を感じるか?
・同世代の歯科医師と価値観が合うか?
対策2:多様なキャリアパスの情報収集
情報収集先:
・多様な臨床研修施設の検索
・歯科系企業のインターンシップ
・歯学部同窓会のネットワーク活用
・ LinkedIn等での業界人との接触
対策3:経済的側面の現実的検討
Q&A:進路選択でよくある質問
検索需要の高い疑問に直接回答しています。
Q:臨床医から研究者への転身は可能?
A:十分可能です 実際に臨床経験5-10年後に大学院進学し、研究者になる方もいます。臨床経験は研究にも活かされます。むしろ現場を知っている分、メリットが多いでしょう。歯科治療に必要な装置を考案したり、歯科用ソフトの開発に活かしたりと、強みは大いにあります。
Q:大学院に進学すると臨床技術が落ちる?
A:計画的に研修すれば問題ありません 多くの大学院では臨床研修も並行して行えます。
むしろ基礎研究の知識が臨床に活かされる場面も多いです。ただ、症例数が多くはなく、かつ、大学では専門分野以外の治療の機会はほとんどありません。そこはキチンとカバーできるように幅広く症例数をあげる方法を探すとよいでしょう。アルバイトで医院の歯科医師として治療することも可能です。ただ、この勤務の仕方はキチンと在籍している大学に確認が必要です。
Q:企業勤務から臨床に戻れる?
A:可能ですが準備が必要です 臨床技術の再研修期間を設ける必要がありますが、企業での経験も歯科医院経営に活かせます。社会情勢に敏感になっているでしょうから、歯科医院を経営していく上で強みがあるのです。ただ、研修先を見つけるハードルが学生時代よりもより高くなることは覚えておきましょう。
まとめ:希望と実際のギャップは「選択の多様化」の表れ
今回の調査で明らかになった「臨床医希望86%→実際79%」の7%ギャップは、決して「失敗」や「挫折」を意味するものではないということです。
この差が示すもの:
1. 歯科医師の職業選択肢の多様化
2. 学生時代では見えない現実への適応力
3. 個人の適性を重視した柔軟な進路選択
重要なのは、この現実を踏まえて情報収集と自己理解を深めることです。
歯学部生の皆さんへのメッセージ
進路選択に「正解」はありません。大切なのは、十分な情報収集と自分自身との対話を重ねて、後悔のない選択をすることです。
あなたの選択が、患者さんのため、そして歯科界全体の発展につながることを信じています。
著者情報
JDCnavi編集部
・歯学部学生・歯科医師専門の情報メディア
・現役歯科医師・研修医による監修体制
・進路相談実績あり
監修者情報
鈴木彰 医師
・神奈川県「ベル歯科医院」院長
・歯科医師歴30年以上
・ 1986年 東京医科歯科大学歯学部卒業
・ 1986年〜1989年 東京医科歯科大学歯学部 附属病院顎口腔機能治療部
・ 1989年 「ベル歯科医院」開設
・ 専門:一般歯科、予防歯科
調査概要:
・ 実施期間:2025年7月
・ 対象:X(旧Twitter)ユーザー
・ 歯学部学生回答者数
・ 歯科医師回答者
・ 調査方法:Xアンケート機能使用
・最終更新日:随時